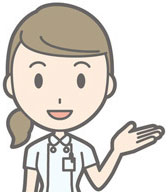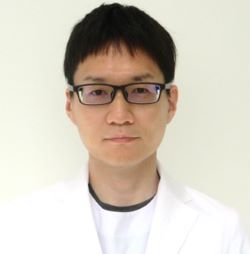診療科紹介
当リハビリテーション科では、患者さん一人ひとりの生活の質(QOL)の向上を目指し、幅広いリハビリテーション治療を提供しています。急性期からの早期リハビリテーション治療をはじめ、専門的なボツリヌス療法や摂食・嚥下リハビリテーションなど、多岐にわたる治療を実践しています。特に、脳卒中後の痙縮治療や、摂食・嚥下障害に対するリハビリテーションには力を入れており、専門のスタッフが対応いたします。また、急性期から回復期、さらには在宅復帰を見据えたリハビリテーション計画を立案し、患者さんの個別ニーズに合わせた支援を行っています。
主な対象疾患と治療について
リハビリテーション科では、急性期の治療が必要な多様な疾患に対応しています。以下のような疾患や症状を対象とし、専門的なリハビリテーション治療を提供しています。
-
脳血管疾患:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血後
運動麻痺や日常生活動作(ADL)の改善を目的とした運動療法、言語療法、認知機能リハビリを実施します。 -
整形外科疾患:骨折、関節手術後(人工関節置換術など)、脊椎疾患
手術後や外傷後の関節可動域訓練、筋力増強訓練、歩行訓練を中心とした運動療法を提供します。 -
呼吸器疾患:肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、呼吸不全
呼吸機能向上のための呼吸訓練、体力回復を目的とした運動療法、誤嚥予防の指導を行います。 -
がん
疲労軽減、筋力維持、ADL維持、体力回復を目指した運動療法や心理サポートを実施します。 -
循環器疾患:心不全、心筋梗塞後
心肺機能の回復を目指した有酸素運動や筋力トレーニングを行い、再発予防のための生活指導を行います。 -
神経筋疾患:パーキンソン病、筋ジストロフィー、多発性硬化症
筋力低下や運動機能とバランス機能の維持・改善を目的とした運動療法を行います。必要に応じて嚥下リハビリや認知機能リハビリを行います。
診療体制
リハビリテーション科専門医1名が常駐し、専門スタッフと協力して365日リハビリテーションを提供できる体制を構築しています。
診療方針
診療方針と主な検査については、当院の「リハビリセンター」の項目をご覧ください。
地域の医療機関の方へ
地域に開かれたリハビリテーション科を目指し、以下の専門外来を開設いたしました。患者さんの治療や評価をご希望の場合は、ぜひ当科までご連絡ください。
痙縮治療外来
脳卒中後遺症、脊髄損傷、脳性麻痺などに伴う痙縮に対して、ボツリヌス療法を実施しています。痙縮により日常生活やリハビリテーションが困難な患者さんに対し、症状の緩和と機能向上を目指した治療を提供いたします。
嚥下外来
脳卒中後遺症などによる嚥下障害を対象とした外来を開設しました。
- 嚥下造影検査(VF検査)による嚥下機能の詳細な評価
- 専門スタッフ(言語聴覚士)による個別の嚥下指導