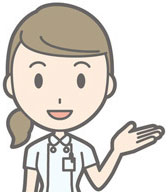診療科紹介

血液内科では、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性白血病やなどの腫瘍性疾患に対する化学療法、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病など血球減少を来す疾患に対する免疫療法を中心に診療を行っています。
国内外のガイドラインや最新のエビデンスに基づいた標準治療を基に患者さんの全身状態を考慮し、血液専門医が診断治療を行い、併存疾患、合併症などを含め全身管理を行います。
主な対象疾患
- 悪性リンパ腫
- 多発性骨髄腫
- 骨髄異形成症候群
- 急性白血病
- 慢性骨髄性白血病
- 慢性リンパ性白血病
- 再生不良性貧血
- 特発性血小板減少性紫斑病など
診療案内
当科の患者さんは、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性白血病、骨髄異形性症候群が多く、治療は化学療法が中心となります。最近は従来の抗がん剤に加えて、分子標的薬(リツキシマブ、ポラツズマブ、ブレンツキシマブベドチン、イマチニブ、第2世代・第3世代チロシンキナーゼインヒビター)、新規薬剤(ダラツムマブ、カルフィゾミブ、イサツキシマブ)、二重特異性抗体(エルラナタマブ、エプコリタマブ)を用いて治療を行い、良好な治療成績が得られています。
特に悪性リンパ腫、多発性骨髄腫は新たな作用機序の薬剤が複数使用可能となり治療の選択肢が増え、再発を繰り返す患者の長期生存が期待されています。標準治療に加え、患者さんの病状、ライフスタイルに応じて、入院での化学療法、外来化学療法での治療を選択でき、患者さん一人ひとりの思いに寄り添う医療を提供します。
「別の病院で血液の病気と診断されたが、意見を聞きたい」という相談に応じることができます。その場合、患者さんの血液検査や画像を持参ください。このようなご相談のある方は、あらかじめ当院の地域医療連携室へお電話でご連絡ください。
血液の病気について
血液は赤血球、白血球、血小板という血球の部分と、血漿という液体成分から成り立っています。これらの血球は骨髄(骨の中心にある部分)でつくられ、骨髄から末梢血へ運ばれます。
骨髄の異常があると正常の血球がつくられなくなります。骨髄の異常を来す病気には、再生不良性貧血(赤血球、白血球、血小板が減る)や、白血病(骨髄で白血病細胞というがん細胞が増えてくる)などがあります。
血液内科は「どんなことをしているのかわからない」「どういうときに行けばいいのかわからない」診療科だと思います。下記を参考に、気になるところがあれば、外来受診をおすすめします。
女性の方へ
以下のような症状はありませんか
- 疲れやすい
- 顔色が悪くなったと他人から言われる
- 不正出血がある、生理の量が多い
貧血の大半は鉄欠乏性貧血です。その原因として胃癌、大腸癌、子宮筋腫や卵巣腫瘍など婦人科の病気が隠れていることがあります。その他貧血の原因としてビタミンB12や葉酸の不足、スポーツ貧血などがあり、腎不全、甲状腺機能低下症等でも貧血になることがあります。
胃の手術をしていませんか
胃の全摘手術を行った人は、手術後2年から5年くらいで貧血になります。ビタミンB12は胃で吸収されますが、胃がないとビタミンB12を含む食品を食べても吸収できません。「巨赤芽球性(きょせきがきゅうせい)貧血」になります。
貧血には鉄欠乏性貧血以外の貧血もあります。重症の貧血では心不全を合併することがありますので「足がはれる」「動悸がする」という症状がでてきます。貧血のある方は男性の方も、胃や腸の検査を含めた全身の検査をうけられることをおすすめします。
症状別情報
以下の症状をクリックすると詳細情報を開きます。
診療体制
スタッフ3名中、血液専門医3名、総合内科専門医2名と、血液専門医、総合内科専門医資格を有するスタッフが、専門知識を生かした血液疾患診療を行います。血液疾患は全身管理が必要なことが多く、幅広い知識を有したスタッフが、豊富な経験を生かして全人的な治療を行います。患者さんの状況に応じて、九州大学病院・関連施設と連携して対応しています。

診療方針
患者さんの病状、背景、思いは一人ひとり異なるため、医師、看護師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士など多職種のスタッフが連携し、最適な医療を提供するように心がけています。患者さんの状況により、入院による治療、外来化学療法による治療が選択でき、生活の質(QOL)を維持した治療が提供できるように工夫をしています。
- 最新のエビデンス・ガイドライン・治療法に基づき、治癒を目指したベストの治療を提供します。
- 標準治療法を行うことが困難な方(合併症を有する方やご高齢の方など)には、一人ひとりの病状、背景、思いを尊重し、最適な治療を提案します。
- 医師、看護師を中心に多職種(歯科医、薬剤師、リハビリ、栄養士など)のスタッフの協力のもと、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供します。
主な検査・設備
クリーンルーム3床を有し、白血病など骨髄抑制の強い化学療法を必要とする治療に活用しています。
地域の医療機関の方へ
血液内科は、今年度も3名体制で造血器疾患の診断・鑑別及び治療を行います。患者さんの状況に応じて、九州大学病院・関連施設と連携して対応しています。鉄剤を処方しても貧血が治らない、血小板減少、リンパ節が腫れている等ありましたら、ご紹介ください。
認定・指定施設
- 日本血液学会研修教育施設
診療実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者のべ人数 | 3,859名 | 4,639名 | 4,568名 | 4,557名 | 4,650名 |
| 入院患者のべ人数 | 9,991名 | 9,675名 | 8,797名 | 8,804名 | 8,755名 |
※2024年度入院患者上位5疾患は以下のとおり
1.非ホジキンリンパ腫 2.多発性骨髄腫 3.白血病 4.骨髄異形成症候群 5.ホジキンリンパ腫
外来担当医表
毎週火曜日・水曜日・金曜日の午前中(新患受付は午前11時まで)
緊急の場合は、上記以外でも対応しますので、病院受付にその旨お伝え下さい。
スタッフと専門領域

血液内科
黒岩 三佳 くろいわ みか
臨床研究部長専門分野
- 造血器腫瘍、血液凝固異常
取得資格
- 日本血液学会 血液専門医、日本内科学会 総合内科専門医
所属学会
- 日本血液学会、日本内科学会、日本血栓止血学会、日本造血細胞移植学会

血液内科
亀﨑 健次郎 かめざき けんじろう
内科医長(血液)専門分野
- 血液疾患、造血器腫瘍
取得資格
- 日本血液学会 血液専門医・指導医、日本内科学会 総合内科専門医、日本造血・免疫細胞療法学会 造血細胞移植認定医、日本輸血・細胞治療学会 認定医
所属学会
- 日本血液学会、日本内科学会 、日本造血・免疫細胞療法学会、日本輸血・細胞治療学会

血液内科
坂本 佳治 さかもと けいじ
内科医師(血液)専門分野
- 血液疾患
取得資格
- 日本血液学会、血液内科専門医、日本内科学会 総合内科専門医
所属学会
- 日本血液学会、日本造血細胞移植学会、日本内科学会